大会のレポートとかが中心になってて、競輪話が少しおやすみになっちゃってましたね🙇
ラインの話、と予告していましたが、新潟の国体で興味を持っちゃった競技用自転車の話を 先に書かせていただきますね🙇。
ということで、まずは、ギアの話からです。

自転車には、ペダルのところ後輪のところにそれぞれギアがついていて、チェーンでつながっています。
ペダルを回転させると、その動力がチェーンで後輪に伝わり、前に進む力になります。
前のギアのことを大ギアとかチェーンリングと呼び、後ろのギアのことは、小ギアとかコグと呼ぶようです。
| 大ギア | 小ギア |
 |  |
大ギアの歯の数と小ギアの歯の数の比率が、ペダルを一回転したときの後輪の回転数になります。
例えば、大ギアが49で小ギアが14の組み合わせの場合、ギア比は3.5となります。
ギア比が高いほどスピードが伸びていきますが、その分、ペダルが重くなります。
重いギアだと踏み出してからトップスピードに持っていくのに脚力を使うので、緩めてからもう一度踏み込むが難しいくなります。
また、ギア比が低いと、ペダルは軽いので踏み出しは良くなりますが、速度を出すにはたくさん回転させる必要があります。
実際に自転車で走ってみるとわかるのですが、回転数を上げてるのも維持するのも案外難しいものです
では、どのあたりのギア比が合うか?というのは、脚質や作戦によるそうです。
踏み込む力や回転数を維持する力、そして、競輪では先行するのか追込みでいくのか、などなど、
いろいろあるとは思いますが、まだまだよくわかってません
またぼちぼち調べておきますね〜🙇
そして、新潟で聞いてなるほど!と思ったのが、ギアの大きさの話です。
ギアの比率だけでなくて、大ギア・小ギアの大きさによっても違ってくるそうです。
大ギアと小ギアはチェーンでつながっていて、これで動力を伝えていますよね?
小ギアが小さいとチェーンの曲がりは急になって抵抗も大きくなってしまうそうです。
逆に小ギアを大きくなると、曲がりは緩やかになってスムーズに回せるそうです。
こう聞くとギアが大きいものの組み合わせの方が良く感じますが、ギアそのものは金属のパーツなので、
ギアが大きくなると重量が重くなってしまって、そういう意味では不利になってしまうそうです。
また、大ギアについても、大きい方がクランクの長さに近くなるので踏み出しが良くなる、
逆に大ギアが小さいと踏み出しは重くなるけれど、後半は割と流せるものだそうです。
比率だけではわかんないもの…なんですね。
(クランクの長さに近くなるとなんで踏みやすくなるんだろう?というのが疑問のままなんですが、
そういうもののようです 何かの機会に誰かに聞いてみます。
何かの機会に誰かに聞いてみます。
さらに、クランクの長さによってもいろいろ変わるそうですが、まだまだよくわかってません
 )
)

クランクはここの部分のパーツです。
なお、競輪では、使えるギアの範囲が決められています。
大ギアは55Tまで。小ギアは12T以上だそうです。
主なギアの組み合わせ表は、 千葉競輪ビギナーズセミナー にありますので、ご参照ください。
競輪学校の入学試験では、49×15(3.27)以内に決められていますが、S級の競輪選手の平均は、3.57だそうです。
最近は4.0倍を越えるギア比の選手も増えてきているそうです。
見ていると、ギア比が高い選手は終盤の伸びがすごいな〜っと思います。
ただ、ギア比が高い分、細かい対応は難しいのかな?とも思います。
また、急にギア比を上げても体に無理が来るそうですので、練習して合わせながらやっていくそうです。
そんな高いギア比への流れに対して、ギア比は変えず回転数で勝負する選手もおられます。
そういうところも気にしながら見ていくと面白いのかな〜っと思います
ちなみに、ギアの組み合わせは 50-14(ごーまるいちよん)のように大ギア小ギアの順で呼ぶそうです。
初めて聞いたときに聞きとれなかったもので ご参考までに
ご参考までに
ということで、ギアのお話でした
ちゃんと書けているかなぁ…。また勉強しておきます
最後に、後藤さん、勉強になりました。ありがとうございました🙇
また、スピードチャンネル スピチャン情報局をはじめ、あちこちのHPを参考にさせていただきました。
[2009.11.01] 誤りがあったので修正しました🙇

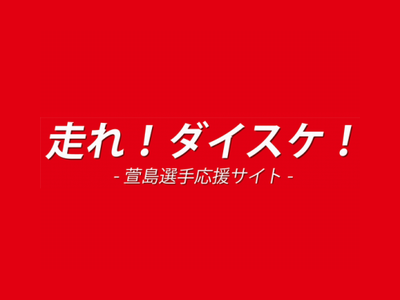
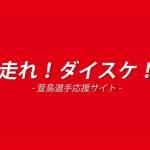
コメント